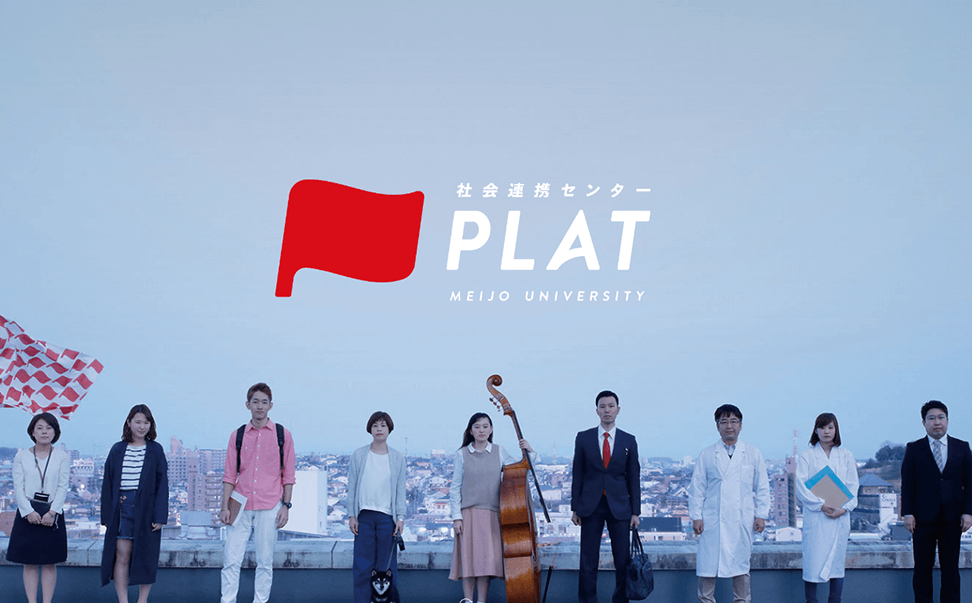大学概要【2024年度実施分】障がい学生支援を担うサポート学生養成事業
学部?部署共同
大发体育官网_澳门游戏网站には、様々な障がいのある学生が在籍しています。障がいのある学生が全ての学生と平等に学修や課外活動等に参加できるためには、教職員はもとより学生による自主的な支援活動が重要となります。本取組は、学生による自主的な支援活動を普及させ、学内に支援の輪を広げることで誰もが自由に学べる大学環境創出の足掛かりとなることを目的とし、学外とも連携を図りながら、幅広く社会に目を向けられる学生を育てていきます。
ACTIVITY
パソコンノートテイク講習会開催 【2024年6月13日(木)】
2024/06/18
6月13日(木)、筑波技術大学から中島亜紀子助教、岡田雄佑特任研究員の2名にお越しいただき、パソコンノートテイク講習会を開催いたしました。本学でパソコンノートテイク講習会を開催するのは初めてということで、参加者19名(学生14名、教職員5名)は、パソコンノートテイクに必要な基本的なところから学びました。
今回は、筑波技術大学が開発したT-TAC Captionというソフトを使用し、初めての連携入力に挑戦。なかなかタイミングが合わなかったり、話者のスピードや、話す内容にキーボードの指がついていかず、途中の入力で止まってしまったりなど、参加した学生は苦労していました。講師の方からは、入力を間違えても、内容が重なったとしても、障がいのある当事者の方にとっては、皆さんの入力が止まってしまうことはそれだけ情報が取れなくなってしまうことに繋がってしまうので、恐れずに入力し続けることが大切であることを参加者に教えてくださいました。今回の研修を通して、学生からパソコンノートテイクができる技術を身につけていきたいといった声が多くあがりました。
障がい学生支援センターでは今後もパソコンノートテイク講習会や練習会を企画し、対応できる力を学生の皆さんに身につけていきたいと考えています。
<学生の声>
?一人で入力をするよりも、連携して入力する方が気持ちは楽だが、お互いのタイミングを見計らって打つことが今まで経験したことがなかったので、練習を重ねていきたい。
?パソコン入力の技術をもっと高めていきたい。
みんなで考えよう!名古屋の街づくり 【2024年11月28日(木)】
2024/12/26
障がい学生支援センターの学生サポーターの一人である情報工学部3年生の榊原悠大さんは、名古屋市発イノベーター育成?ビジネス創出プログラム「NAGOYA BOOST10000」で活動をされています。榊原さんは車いすユーザーの方であり、日常生活の中での移動や生活全体のバリアに対する問題意識を持ち続けており、自身で「FukusITo」を立ち上げられました。
今回の対話会は、榊原さんが主体となって会を企画いたしました。ゲストユーザーに脳性麻痺の森さん(社会福祉法人AJU自立の家)をお招きし、榊原さんと一緒に活動をされている㈱デンソーの伊丹様、フリーランスで活動をされている加藤様、学生サポーター、教職員の計12名で榊原さんの取組に対する意見交換と、障がいのある方々にとって暮らしやすい生活とはについて話し合いました。森さんからは車いすユーザーの方が過ごしやすくなるよう取り組んできた活動について、榊原さんからはこれまで感じてきたバリアについてお話をされました。参加者からは実際に困っている現状を見ることはあっても、どう対応をしたらよいかわからないといった声が上がり、それに対してもっと積極的に声をかけてほしい、大丈夫であれば大丈夫だと答える、今の状況は助け合いの雰囲気がないと指摘されました。
また、最近よく見かけるヘルプマークについても、ヘルプマークを付けている人をたくさん見かけるが、何をどう助けたらよいのかわからない、何に困っているのか、といった声が上がりました。
当事者目線について今まで真剣に考える機会が少なかったサポート学生らは、今回森さん、榊原さんからの話を聞いて、自分たちにできることはなにかを学べた機会でした。
障がい学生支援センターでは、今後も榊原さんと一緒に対話会の企画を予定しています。
また、榊原さんたち「FukusITo」で開発しているアプリについても、今後体験会を開く予定です。
<学生の声>
?特に日本は、声を掛けにくい風潮があると思うのですが、困っている人は声を掛けられて困ることはないということが聞けたので、心理的に声を掛けやすくなりました。
?アメリカ、オーストラリアは助けてもらえるシステムがあるが、日本にはない。教育から考え直していかなければならない。
?自分の中に助けたいという意識があっても、意外とハードルが高いことをあらためて気づいた。
?「助けたい」と「助けてほしい」という思いを繋げるのは大変ではあるが、大事なことだと思った。教員になる立場として、障がいのある方と関わる機会を増やしていきたい。
名城オリジナルのコンテンツを作成しよう その1【2024年10月~1月】
2025/01/17

どのように進めたらよいか相談する学生サポーター
現在障がい学生支援センターでは、学生サポーター4年生が中心となって、今後学生が困ったときに活用できるようなコンテンツ作成に取り組んでいます。特に今年度4月当初は、新入生が履修登録に大変迷い、障がい学生支援センターに相談があったことを学生サポーターに話をしたところ、手伝いたいと申し出てくれました。学生らは、新入生の履修登録を一緒に行った経験から、新入生が履修登録を自分で行うためには、どのように考えたらよいか学生目線でマニュアルの作成に取り組みました。4年間の経験の中から、何が一番困ったのか、どういう点に気を付けて作成したらよいのか、話し合いを進め、新入生に紹介できるような資料が出来上がりました。
先輩サポーターが作成した資料は、今後新入生に紹介し活用したいと思います。
また、このコンテンツ作成の活動については、後輩が引き継ぎ、更なる名城オリジナルコンテンツの充実を目指していく予定です。
障害理解に関する勉強会の実施「発達障害について学ぼう」 【令和7年1月30日】
2025/02/05
発達障害について、皆さんはどんなイメージを持たれますか?
障がい学生支援センターでは、発達障害について少しでも理解をしていただけるきっかけづくりとして、今回勉強会を開催いたしました。講師には、『名古屋市障害理解に関する講師派遣事業』より、社会福祉法人『名古屋手をつなぐ育成会』副理事長 濱田智恵実様が講師となり、前半はご自身の発達障害がある子どもの子育てについて、後半は4つの擬似体験を取り入れながら、発達障害のある方に対してどのように接していくとよいかなど、お話をされました。特に「かいてみよう」という擬似体験(2人1組のペアとなり、図形が記されたカードを見ながら、ペアになった相手に図形を口頭で説明し、鉛筆でその形を記載してもらう)では、どのように相手に伝えれば伝わるのか、苦労している様子が見受けられました。言葉だけの説明では相手に伝えづらいこと、その人に合わせた説明の仕方について工夫することが必要であることを学びました。
最後に講師の濱田様より、障がいのある人と接するときには、“その人の事を知りたい”、という気持ちから出発してほしいという言葉を参加者に向けて伝えられました。
<参加者の声>
?今日の講習はとても意味のあるものでした。在学中に何回か障害に関することは学習していました。学習してから時間が経っていましたので、これから先につながる情報をたくさん学ぶことができました。
?擬似体験において、自分が無意識に曖昧な言葉を使っていることに気がつくことができました。障がいに理解のある人になって助けになりたいと思いました。
?発達障害もいろいろあって、その事を理解できず、困っている方も多いのかなあと思った。
対話会の開催 【2025年2月7日(金)】
2025/02/12
「ディスアビリティのある人が起業家であることにあなたはイメージがつきますか?」
そんな問いかけから対話会が始まりました。
今回は、障がい学生支援センターの学生サポーターの一人である情報工学部3年生の榊原悠大さんが主体となって、企画?運営をいたしました。ゲストユーザーは、先天性二分脊椎症の松田千恵子さん(「株式会社ARISAN」CEO、「一般社団法人SD&研究所」Director)をお招きし、学生と教職員の計10名で松田さんが起業家として歩んできた道のり、何を大切にしてきたのか、そして今後の展望などのお話を聞かせていただきました。松田さんは、自身が車いすユーザーでもありますが、障害者のエンジニア育成事業の先駆けとなるNGOを設立。単身インドネシアに進出し、インドネシア在住の障がいのある方々と一緒にコミュニティを作ってこられました。松田さんは、「well-being」(個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念)を大事にしておられ、時代に合わせて自分の生き方を変えてこられたと熱く語られました。
参加者は、松田さんの熱量を感じながら、自分自身の生き方を振り返りつつ、これからの生き方のヒントを掴んだようでした。