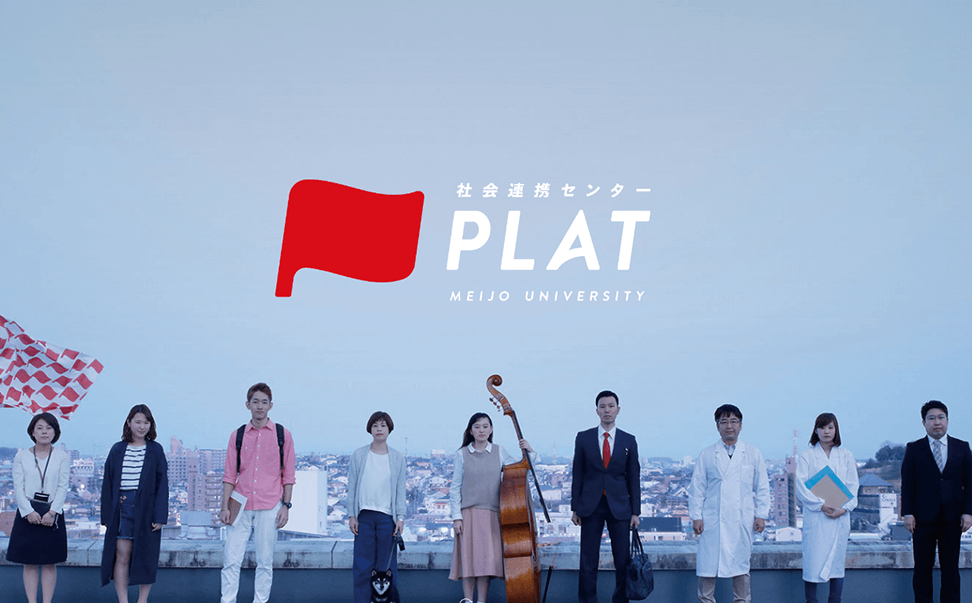トップページ/ニュース 経営学部の澤田貴之教授の公開授業でJAL航空みらいラボの原田克人氏が講義
テーマは 「世界と日本の航空業界の現状と課題 ~サステナブルな航空輸送に向けて~」
 講師を務めたJALみらいラボ産学共創部長の原田氏
講師を務めたJALみらいラボ産学共創部長の原田氏
-
 講師の原田氏を紹介する経営学部の澤田教授
講師の原田氏を紹介する経営学部の澤田教授
経営学部の澤田貴之教授の「アジア企業論」で11月7日、株式会社JAL航空みらいラボ産学共創部の部長である原田克人氏を招いた公開授業が共通講義棟南で実施されました。キャリアセンターとエアライン就職サポートプログラム(M-CAP)が協力し、経営学部と航空業界に関心のある本学学生約150人が参加しました。
インバウンド誘客の重要性
講義はまず、昨年1年間の世界の航空機利用者数の3択クイズからスタート。2000年以降、約3倍に伸びた昨年の利用者数は約50億人で、アジア?オセアニア地区がその成長を牽引してきました。今後は利用者数の成長が見込まれるインドや東南アジアと世界経済の中心地北米との経由地として、日本を含む北東アジアに大きなビジネスチャンスがあると説明。しかし、日本の国際空港は国家的なプロジェクトとして開発されている韓国や中国などの国際空港に比べて規模や利便性で劣ることから、現状のままでは今後の乗り継ぎ需要拡大を受け止めきれない可能性があると指摘。原田氏は「日本の人口減少が進展していく中で、経済の縮小を補うインバウンド誘致は日本経済にも重要である。インバウンド誘致の推進と今後拡大するアジアの流動需要を取り込むためにも、日本も他国に劣らないような国際空港の整備?機能強化を考えていく必要がある」と話しました。
お客さまへの最高のサービスを支えるのは社員の幸福の追求
 JALの企業理念を熱く語る原田氏
JALの企業理念を熱く語る原田氏
 講義に聞き入る学生たち
講義に聞き入る学生たち
本学の学生数は約1万5000人で、JAL(日本航空)の社員数もほぼ同じ。グループ企業も含めると約3万8000人を抱える航空業界大手のJALは、2010年の経営破綻とコロナ禍を踏まえ、企業理念の土台を「全社員の物心両面の幸福の追求」とし、「JALフィロソフィ」で社員がもつべき価値観を共有。原田氏は「JALではコロナ禍の教訓から、現在ローコストキャリア(LCC)や非航空事業を強化してリスク耐性を高める事業構造改革に取り組んでいる。『安心?安全』と『サステナビリティ』を重点テーマに、全社で力を合わせてお客さまに喜ばれる価値を提供していきたい」と力を込めました。
企業の持続可能な成長に不可欠な「ESG経営」と価値創造の実現
JALがサステナビリティ(持続可能な成長)のために戦略の最上位に据えているのが「ESG戦略」。環境問題への対応では、2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けてGX戦略を策定し、省燃料機材の導入やSAF(持続可能な航空燃料)の活用などによってCO2排出量の削減を目指しているという。また、社会課題である日本の人口減少問題に対しては、業界横断でグランドハンドリング協会を設立して空港業務の効率化や生産性向上に取り組むほか、多様な人材の活用などで人手不足対応を進めています。そして原田氏は、JALでは「移動を通した関係?つながりを増やすことで、社会の持続的な発展と人々のウェルビーイングに貢献すること」を全社の目標としているとし、取り組みの一例として25歳以下の若者を対象とした「JALカード?スカイメイト運賃」を紹介したうえで、若者による新しい関係?つながりの創出、その発信への期待を語りました。
学生からは、ESG経営における機材更新やSAFの活用におけるコスト問題について鋭い質問がありました。原田氏は、この悩ましい問題について、インバウンドでの外貨獲得や産業界を巻き込んだ取り組みにより厳しい現実を乗り越えていく必要性と気概を伝えました。
-
 質問する学生
質問する学生
-
 M-CAPの活動を説明する濱崎さん
M-CAPの活動を説明する濱崎さん
学生たちは、JALが直面している諸問題やその解決に向けた具体的戦略にふれたことで、企業経営の在り方を学ぶとともに、自らの将来の在り方を考えていく機会になりました。