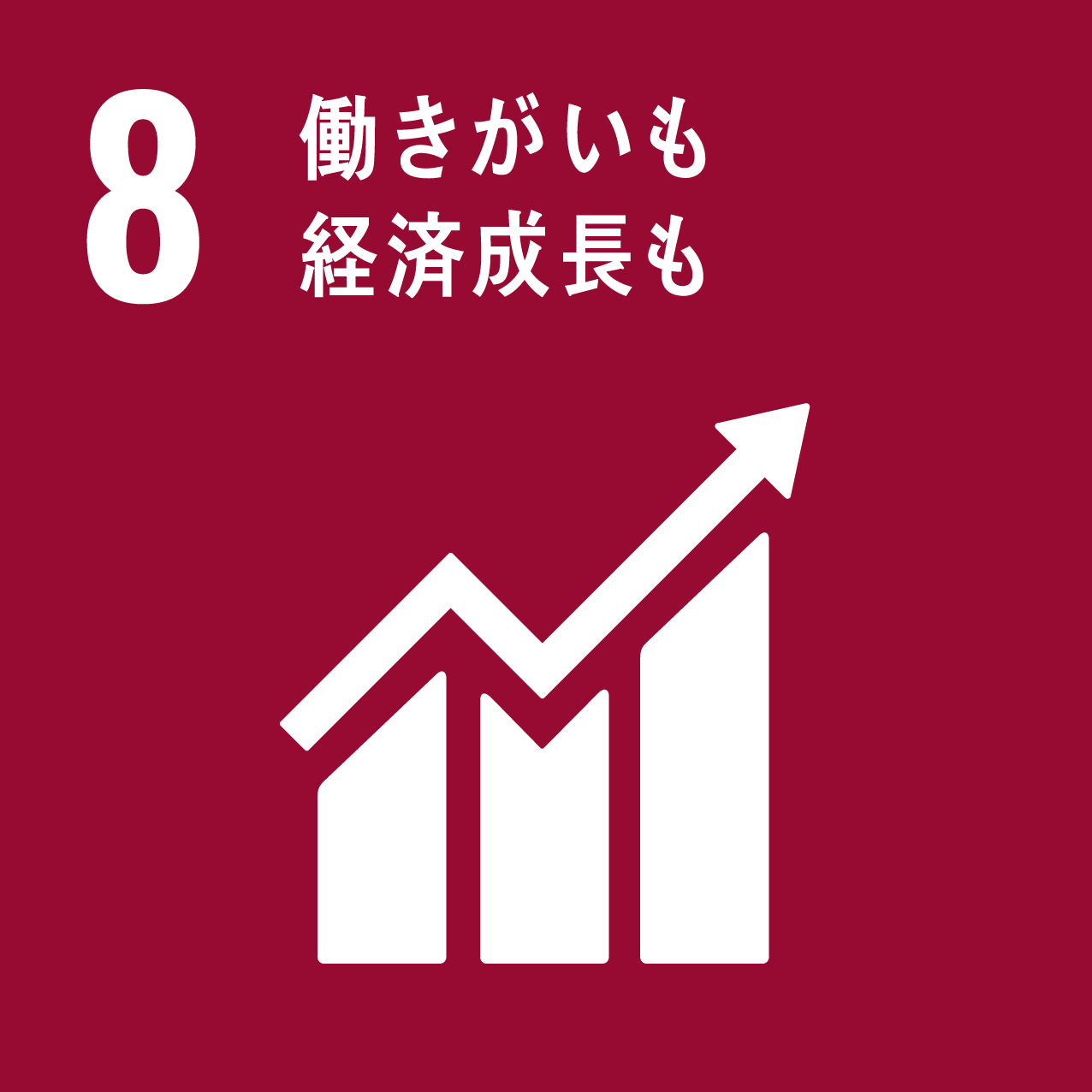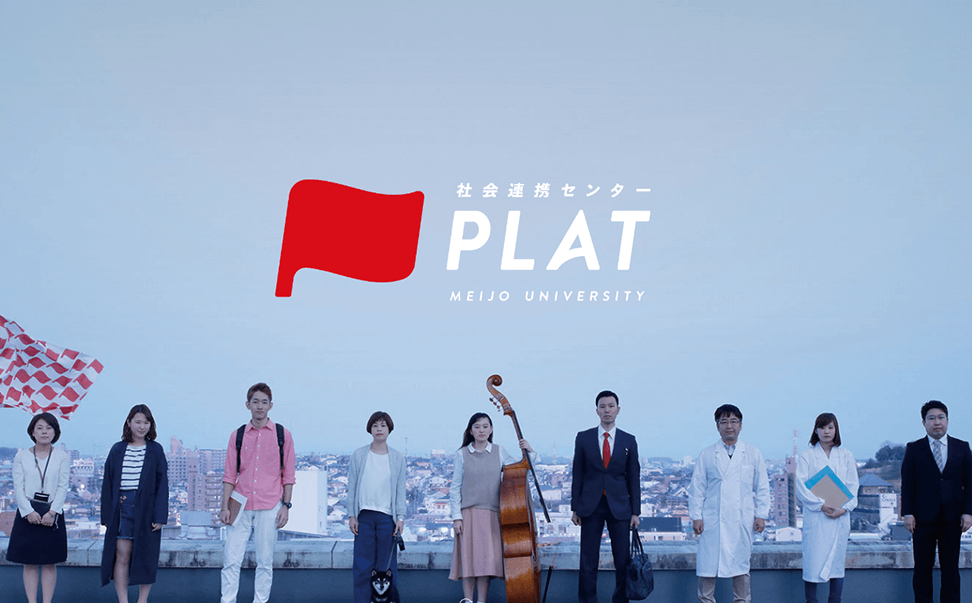大学概要【2024年度実施分】国際フィールドワークI(英語圏):東南アジアの英語通用国で実践する現地学生との協働型PBL学修
外国語学部
大学での学びは社会の中でどのように活かされるでしょうか。本事業では、シンガポールとマレーシアでの現地研修における同地の政府関連機関や日系企業が抱える問題を、現地の大学生との協働や調査活動を通して解決します。このような課題解決型学習を行うことで、これまでの学修の成果を実践できるとともに、国や地域の枠組みを超えたグローバル人材となるために求められる挑戦心や探求心を向上させることを目指します。
ACTIVITY
マレーシアでのPBLと新たな仲間たち
2025/01/31
2024年9月1日(日)から9月11日(水)まで、「国際フィールドワーク(I)(英語圏):東南アジアの英語通用国で実践する現地学生との協働型PBL学修」が実施されました。
本フィールドワークは、参加学生が現地企業の抱える経営上の課題や問題について現地の大学生との協働により解決策を提起する、課題解決型授業(PBL)です。
今回は東南アジア諸国のうち英語通用国であるシンガポールとマレーシアを対象とし、7名の学生が参加しました。
第1日目となる9月1日は中部国際空港からシンガポール?チャンギ空港に到着し、現地のコーディネーターの方の出迎えを受け、陸路でマレーシアのジョホールバルに到着しました。
すでに4回の事前研修を終えてはいたものの、自動車で国境を超えるという日本では経験できない場面に、参加者は改めて本フィールドワークへの期待を高めていました。
マレーシアでのPBLで得た成果と新たな仲間たち
2025/01/31
2024年9月6日(金)から9月10日(火)まではマレーシアを拠点に活動しました。
マレーシアでの課題解決型授業(PBL)の実施先はハードロック?カフェ?プテリ?ハーバー(HRCPH)でした。
最初にHRCPHを訪問し、広報責任者の方からハードロック?カフェの歴史や店舗の特徴などのお話を伺いました。
その後、参加学生は2つのグループに分かれ、それぞれ「セブンティーン」と「プーティン」と命名しました。そして、マレーシアでの協働大学であるマレーシア工科大学(UTM)の学生の皆さんとともに予行演習として与えられた課題を検討し、報告しました。
報告終了後は、マレーシアでのPBLの課題が提示されるとともに、9月4日(水)までの3日間にわたり大型ショッピングモールなどで利用者へのアンケート調査を行い、課題を解決するために必要な情報を収集しました。
9月5日の15時からはHRCPHで最終報告会が行われ、「セブンティーン」と「プーティン」の2つのグループがHRCPHの持つ経営上の課題に対する解決策を提案しました。
この間、ジョホール市内の私立病院であるケンジントン?グリーン?スペシャリスト?センターを訪れ、医療機関を取り巻く現状や様々な取り組みなどの説明を受けるなど、PBLの課題解決に加え、訪問先であるマレーシアの実情についてもよりよい知見を得ることができました。
参加学生からは「ここに来てから、どこに行っても「多文化共生」を実感し、とても面白いです。」「英語に関しても不安を抱いていましたが、自信を持って積極的に自分から話すことでよりこの旅が楽しくなっていると感じます。」「マレーシアでの5日間のフィールドワークを通して、現地の学生との交流も深まり、かけがえのない経験をすることが出来ました。」といった感想が寄せられ、大发体育官网_澳门游戏网站で培った英語の運用能力がマレーシアでより向上しことや、現地の学生との交流の深まったことが分かりました。
なお、今回の取り組みについては、UTMの公式ウェブサイトでも紹介されており、大发体育官网_澳门游戏网站の学生だけでなくUTMからの参加者にとっても意義の大きい試みになったことが分かります。
*マレーシア工科大学公式ウェブサイト
https://news.utm.my/2024/10/faculty-of-management-utm-and-meijo-university-japans-global-immersion-research-project-2024-innovative-solutions-for-hard-rock-cafe/
シンガポールのPBLでのさらなる成長と将来の進路のために踏み出した大きな一歩
2025/01/31
2024年9月6日(金)から9月10日(火)まではシンガポールが拠点でした。
シンガポールでは、ハードロック?カフェ?チャンギ空港店(HRCCA)が課題解決型授業を行いました。また、協働大学はジェームズ?クック大学シンガポール校(JCU)の皆さんでした。
今回も参加学生は「セブンティーン」と「プーティン」の2つのグループに分かれ、HRCCAの最大の課題である集客力の向上のための施策を検討するため、4日間にわたり共同でアンケート調査や解決策の立案などを行いました。
9月9日(月)の15時30分から始まった報告会では、「プーティン」と「セブンティーン」の2つのグループがアンケート調査の結果に基づき、HRCCAの集客力向上のための施策を提案しました。HRCCAからは担当者2名がオンラインで参加し、2つのチームによる報告や提案の内容について意見が寄せられました。
この間、9月7日(土)は午前中にシンガポールの日本大使館に併設されているジャパン?クリエイティブ?センター(JCC)を訪問しました。JCCでは同センターが行ったシンガポール人の撮影した日本の風景写真の展覧会を見学するとともに、JCCイベントチーム?マネージャーの副田景子さんから、日本とシンガポールの関係やシンガポールにおける日本文化の普及のあり方などについてお話を伺いました。また、午後はシンガポール国立大学(NUS)を訪問し、NUSビジネススクールに在籍する倉瀧健一郎さんのお話を伺いました。倉瀧さんからは、日本で働くことと外国で学び、働くことの意味を考え、今後のキャリア形成に向けてどのように取り組むべきかという重要な視点が提起されました。
また、9月10日は期間中で唯一の自由行動の日であり、参加学生はCUの有志とともにユニバーサルスタジオシンガポール(USS)に行き、交流を一層深めることが出来ました。
参加学生からは「シンガポールでは対面の発表ではなく、オンラインで行われました。相手の顔が見えないため、対面よりも緊張しましたが自分達の発表を自信を持って伝えることができました。さらに、今までの活動の成果を最終発表で発揮することができたと思います。」「倉瀧さんのお話から、卒業後のキャリアを見据えて、残りの学生生活の過ごし方について見直したいと考えました。目標を達成するために、明確で正確な目標を立て、自分の行動についてもなぜ行なっているのか意識するようにしたいです。」「この10日間を通して、マーケティングだけでなく、異文化間の違いであったり、街頭調査をしたことによって、自信をつけることができました。」といった感想があり、新たな学びと今回のフィールドワークが将来の進路のための重要な一歩になったことが分かりました。