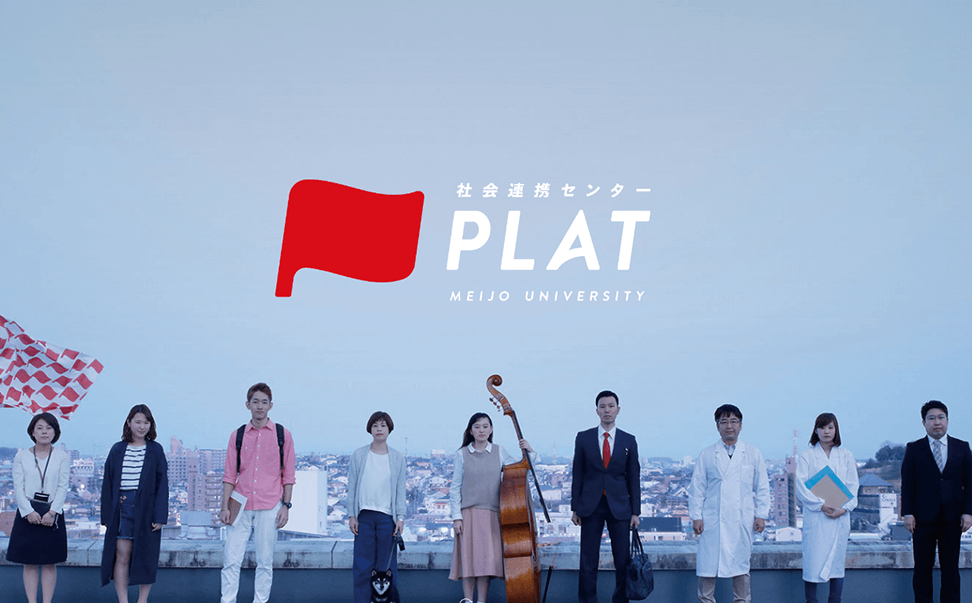大学概要【2025年度実施分】三河湾の水質環境を学び、考える
大学院総合学術研究科
本プロジェクトでは、海洋観測を通して総合学術研究科の研究分野の一つである海洋環境研究の基礎を体験してもらいます。本学と、愛知県水産試験場および国土交通省中部地方整備局三河港湾事務所の連携により、三河湾域の海洋環境の実態や環境保全に係る基礎知識を学ぶことができます。
ACTIVITY
船舶による三河湾の海洋調査
2025/08/22
2025年8月21日に実施した大学院総合学術研究科の海洋実習で、船舶に乗船して三河湾の海洋環境調査を行いました。本年度は全学的に参加募集をかけ、総合学術研究科の院生や教職員だけでなく、農学研究科、人間学部、理工学部、都市情報学部、農学部の学生も参加しました。全国有数のアサリ稚貝の発生場所である六条潟、人工的な埋め立て地に囲まれた大崎地区窪地や三河湾口に位置する中山水道航路などの湾内でも環境が大きく異なる計6ポイントで水質調査(透明度、水温、塩分、溶存酸素、クロロフィル)、砂泥採取、プランクトン採取といった様々な調査を行いました。参加した学生は、時折船が大きく揺れるなどの困難もありましたが、積極的に作業を行いました。船上で得られたデータを愛知県水産試験場で解析し、特に三河湾の海の水温と溶存酸素が深度によってどのように変化しているか理解を深めました。
海洋プランクトンの採取と顕微鏡観察
2025/08/22
2025年8月21日に実施した大学院総合学術研究科の海洋実習において、三河湾から採取したプランクトンを愛知県水産試験場の設備をお借りして顕微鏡観察しました。水産試験場にはプランクトン観察のプロフェッショナルが在籍しており、魚類に有害な毒素をもつプランクトンなど、海環境や漁業の現状と関連したご説明をいただきました。参加学生は顕微鏡観察したプランクトンについて興味をもち、積極的に質問することで理解を深めることができました。
三河湾環境の過去と現在を学び、未来を考える
2025/08/22
2025年8月21日に実施した大学院総合学術研究科の海洋実習では、船舶に乗船しての海洋現場による環境観測だけでなく、三河湾環境の研究や整備に携わる専門家による講義を受けることで、理解を深めることができました。
水産試験場の漁場環境研究部?谷川万寿夫部長からは「伊勢?三河湾の漁場環境」と題して話題提供がありました。そこでは環境調査で収集したデータをもとに三河湾の現状を知り、現在どのような取り組みが行われているかを考えました。また、国土交通省三河港湾事務所の鈴木真也課長からは「三河湾における干潟?浅羽と環境改善に向けた取り組み」と題して三河湾の環境改善に向けた取り組み状況をご説明いただきました。
本学大学院総合学術研究科の鈴木輝明特任教授からは、大发体育官网_澳门游戏网站と中部電力との産学連携活動の成果として、三河湾の環境悪化の原因が河川から流入する栄養塩の不足にある可能性についてお話いただきました。鈴木教授は「海洋環境の悪化によって近い将来には魚介類が食べられなくなるかもしれない。これからは海洋環境に関する研究の重要性がますます高まってくる。」と話しました。