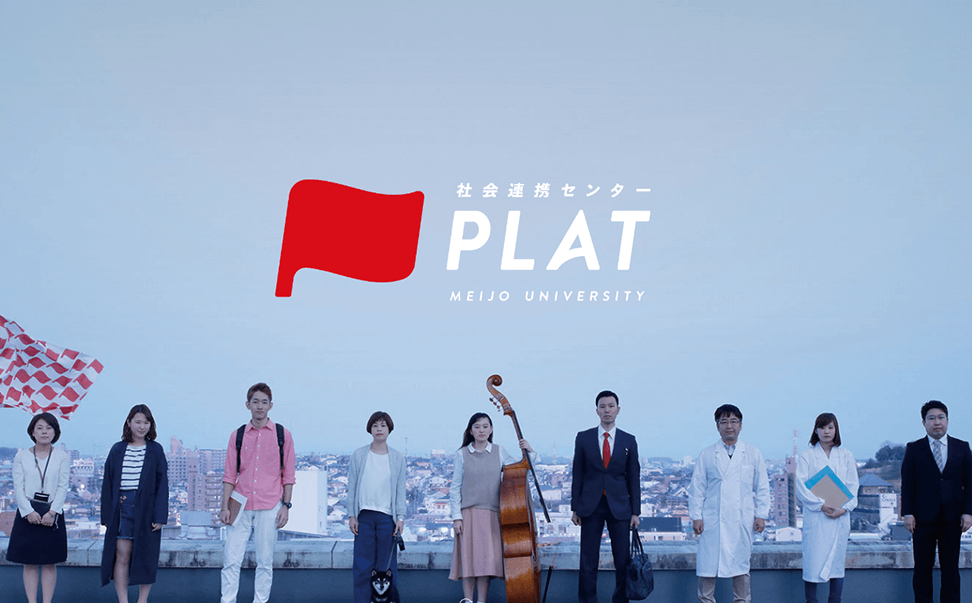特設サイト第127回 「生薬とは?」
活発な秋雨前線により、10月は晴れの日が少なかったと聞きます。また、朝晩の気温も下がっており、快適な自転車生活もそろそろ防寒の準備が必要になってきています。
さて、今回は処方解説をお休みして、「生薬とは?」の復習です。
人類は長い歴史の中で、身のまわりの植物や動物、鉱物のすべてを含む天産物から、病気と戦う武器として数多くの「薬」を見つけ、その知識を大切に伝承してきました(「新訂生薬学」(南江堂))。この天然産物をそのまま薬として利用しているのが「生薬」です。教科書的に定義しますと、「植物や動物、鉱物の適当な部分を取り分け、胃薬としての価値を失わず、利用しやすく、保存や運搬にも便利な形に加工したもの」を「生薬(crude drug)」とよびます。加工の基本は乾燥で、日本薬局方の生薬総則では通例60℃以下で行うとされています。乾燥することで、例えば植物、動物などがもつ酵素反応を妨げ、成分などの分解?変性を抑制するとともに、カビの発生や腐敗、虫害を防ぎます。また、乾燥することで重量も軽くなり、また嵩も減るなど、生のままよりは保存しやすく、また運びやすくなるという効果があります。ときには、目的に合わせて、湯通ししたり、蒸したり、炙ったりするなどの特別な加工を施すこともあります。薬効を変化させたり、毒性を減じたり、また虫害を防ぐなど保存のためにといろいろな加工を行うのですが、これらを学ぶたびに、先人の苦労というか、知恵を感じます。
わが国では、医薬品としての生薬は日本薬局方や日本薬局方外生薬規格などの公定書に収載され、そこで規格が定められています。ニンジンを例にとりますと、ウコギ科(Araliaceae)オタネニンジン(Panax ginseng)の根を用いる生薬とされています。このように、生物種と使用部位が決まっており、それらをセットで「基原(きげん)」とします。同じウコギ科ニンジン属のものであっても、種が異なると、医薬品としての「ニンジン」ではありません。基原は医薬品としての生薬の判定基準なのです。
また、細い根を取り去り、またこれを軽く湯通ししたものを白参、蒸してから乾燥したものを紅参として使い分けています。ニンジンは強壮、健胃、制吐、止瀉の作用をもつとされており、蒸してから乾燥すると、これらの作用が増強されると言われています。また、個々の生薬には特有の「におい」や「味」があり、それらも生薬の判定基準となる一方で、「色」は時間の経過により変化することも多いためか判断基準とされます。われわれの五感を通して、その鑑別が可能であるということも生薬の特徴の一つではないでしょうか。

人参(切断生薬)

ニンジン(全形生薬)
さらに、生薬は天然から得られた医薬品ですから(「天然物医薬品」)、新薬(合成医薬品)のように単一化合物の「化学医薬品」ではなく、有効成分を取り出すことなく利用する「未精製医薬品」、すなわち「混合物」です。天産物であり、混合物の医薬品であることから、同じ基原植物を利用しても、産地や天候により成分やその含量に変動があることは容易に想像されます。そのため、生薬の品質は既知の有効成分の含量が多いものというよりはいつも同じであること、一定であることが望まれます。医薬品であれば、すべて品質の斉一性が求められますが、生薬は独特です。野菜や果物、水産物などであれば、豊作や不作、豊漁や不漁など年による変化があり、受け入れざるを得ないのですが、そうはいかないのが薬です。また、こういった生薬を複数組み合わせて利用しているのが漢方薬ですから、会社ごととはいえ、一定の品質を保つように漢方エキス製剤を製造しているメーカーの努力はすごいものです。
今回は漢方薬を構成する生薬について、今一度認識していただきたくて、生薬のお話をしました(^^)。
(2025年10月31日)