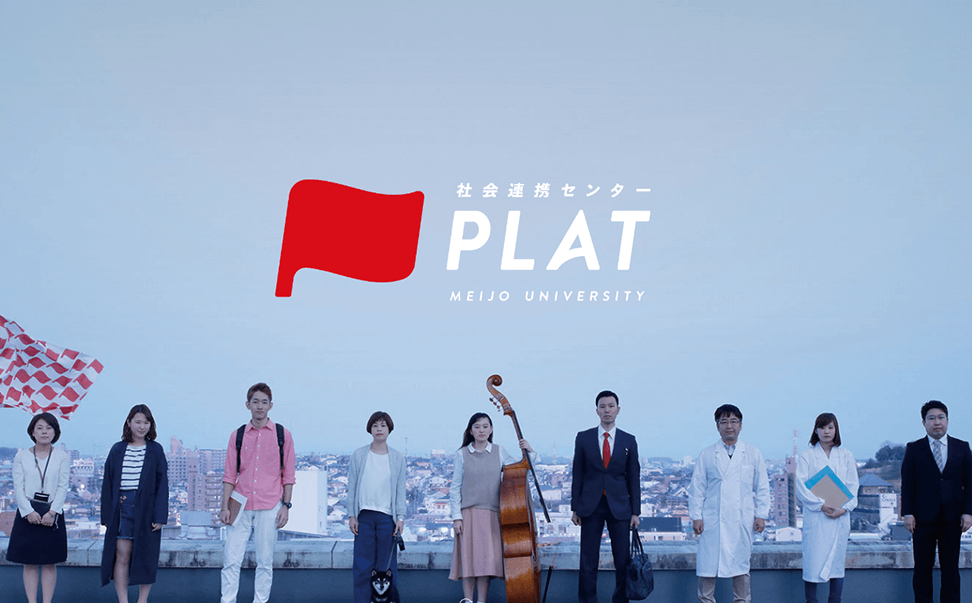大学概要【2025年度実施分】SDGsの課題に取り組む公務員に学ぶ
人間学部
人間学部の学際的なカリキュラムは公務員試験に適合的で、多くの卒業生が公務員として活躍しています。このプログラムでは、SDGsについて学びながら現代社会のさまざまな課題を抽出します。そして、そうした課題に取り組んでいる公務員の方の講話などを通して、現代社会で公務員が果たしている役割について学びます。以上のような活動を通して、公務員を目指す学生をより着実に支援します。
ACTIVITY
今年度も日進市の教材動画を作成する予定です
2025/09/15
2024年度の学びのコミュニティの活動で、日進市の小学生が市役所のことを学ぶ教材動画を作成しました。
この様子は、以下のページに紹介されています。
「遊び心あふれる市役所紹介動画で小学生の学びを豊かなものに」
/mag/manabi/project/article-enjoy-2025-01.html
今年度は、給食に関する動画を作成することになりました。7月14日、日進市の学校給食センターを見学しました。岡田所長さん、学校教育課の桃原課長さん、浅井課長補佐さんから、給食センターのお仕事や学校給食をつくる際のご苦労などをうかがいました。
給食をつくるお話はどれも興味深いものばかりでした。子どもたちに人気のメニューは揚げパンですが、これは調理が大変です。油を有効に使うようにメニューの編成を考える必要もあります。地産地消も目指されていますが、日進のセンターでは一度に9,800食をつくるので、それだけの材料が確保されてようやくメニューとして提供することができます。日常的な給食の場面で、残菜量が減るような働きかけの方法もあるようです。子どもたちからの感謝のお手紙が調理員さんのところに届くこともあるそうです。
大きなしゃもじを使って巨大ななべの具材をかき混ぜるのはとても大変そうでした。調理場は、さながら給食をつくる「工場」です。調理員さんたちの思いや、給食づくりの工夫、給食センターの仕事のしくみなどがわかる、楽しい動画を考えたいと思います。
陶磁器のまち瀬戸の一端を学びました
2025/09/15
8月7日には、陶磁器のまち瀬戸について学びに行きました。
陶磁美術館の陶芸館で、作陶体験をしました。まず、講師の先生から、粘土の取り方、手回しろくろの使い方、底から縁を盛り上げる手順、土を削る道具の特徴などを一通り習います。各自が思い思いの作品をつくりました。2ヶ月ほどで焼きあがるようで、できあがりが楽しみです。この日は夏休みだったとはいえ、体験室はほぼ満員の人気でした。
その後、ラウンジに移動して、瀬戸市の小学校の先生から、瀬戸の子どもの陶芸の取り組みについてお話をうかがいました。瀬戸市の小学生は秋の陶芸展に向けて6月に作品づくりを行い、クラスで1~2作品が選ばれて焼かれ、市展覧会に出品されるということでした。児童の親たちも経験してきていることで、瀬戸市の人々にとって陶芸が大変身近なものであることがうかがえました。
お話を聞いた後、瀬戸市中心部に移動、散策しながらまちの様子を観察しました。空きビルをセルフリノベーションして開店したカフェは、瀬戸のまち再生プロジェクトの嚆矢ということでした。
公務員になった卒業生との座談会
2025/11/18
11月6日、公務員として活躍している卒業生お2人をゲストとしてお招きし、公務員をめざす在学生との座談会を開催しました。
前半は事前に用意されたいくつかのテーマに沿って、公務員を志望するようになったきっかけや、公務員試験に向けての準備、公務員として現在取り組んでいる仕事などについて、ゲストのお2人にお話しいただきました。後半はフリートークとなり、公務員試験で苦手だった科目の克服方法や、学生時代の過ごし方、公務員としての仕事のやりがいなどについて、参加者からのさまざまな質問にお答えいただきました。
参加した学生にとっては、自分と同じ学部で学んだ先輩の言葉にはほかにはない説得力があり、将来を考える上で非常に有意義な機会となりました。