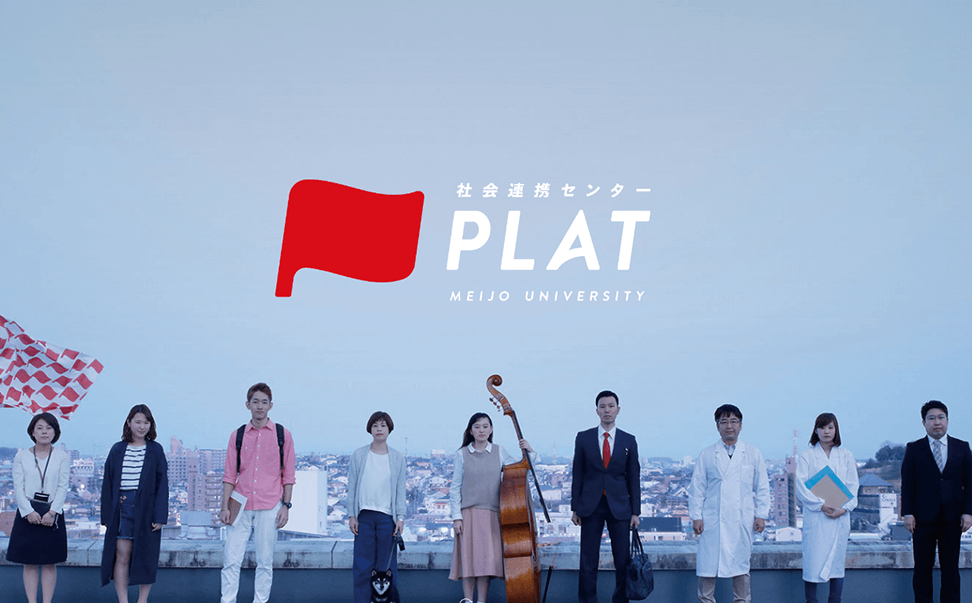特設サイト第38回 漢方処方解説(14)小柴胡湯
今回取り上げる漢方処方は、小柴胡湯(しょうさいことう)です。
小柴胡湯は、柴胡(さいこ)、黄芩(おうごん)、半夏(はんげ)、人参(にんじん)、大棗(たいそう)、甘草(かんぞう)、生姜(しょうきょう)の7つの生薬から構成されています。古典によれば、感染症などの外感病が少し進行し、徐々に身体の内部にまで達してきた時期に用いるとされ、そういう「少陽病期(しょうようびょうき)」に欠かせない処方として知られています。
主薬である柴胡は、薬用部位として根を用います。基原植物であるミシマサイコは、八事キャンパスでも順調に育ち、うっそうとしてきました。根を収穫するには3年ほどかかると言われますので、後2年ほど待たないといけません。
漢方医学には、患者さんを仰向けに寝かせ、治験者がお腹のあちこちを押したり、さわったりして病気の具合を探る「腹診(ふくしん)」という診断法があります。興味深いことに、脈をみること(「脈診」)や舌の様子を観察するような診断法(「舌診」)は中国や韓国にもありますが、この「腹診」は日本独特のもので、江戸時代に始まったとされます。
患者さん自身が「わき腹からみぞおちにかけて、なんとなく重苦しい感じがする」とか、腹診で「肋骨の下を押したところ、張っている感じがする」という状態を「胸脇苦満(きょうきょうくまん)」と呼びますが、それがまさに小柴胡湯を用いるサインとされます。
ちょうど、左右の肋骨の下あたりの抵抗感は、肝臓の腫れを想像させるような症状であることから、日本では小柴胡湯をウイルス性肝炎など肝障害の治療に応用しました。日本や東アジアは、その他の地域に比べてウイルス性肝炎に悩まされてきた地域ですから、肝障害への応用は当時のメディカル?ニーズに合致したものだと思います。
臨床においても、小柴胡湯は慢性肝炎から肝硬変、肝がんへの移行を抑制するという論文が報告されるなど、その有用性を支持するデータが盛んに報告されました。しかしながら、インターフェロン療法がウイルス性肝炎の治療に導入された後、小柴胡湯と併用すると副作用として間質性肺炎が発生する頻度が上がることが報告され、直ちに両者の併用が禁忌となりました。
小柴胡湯の肝障害への応用は、我が国で開発された使用法であると言えますが、最近では肝障害の治療自体にあまり使われなくなっております。中国の古典的処方集で、漢方医学の古典として最も重要視されている「傷寒論」「金匱要略」に収載されているように、抗炎症作用や免疫調節作用をもつ「少陽病期の妙薬」として上手に活用していきたいものです。
(2017.6.27)